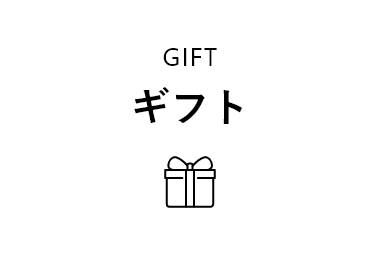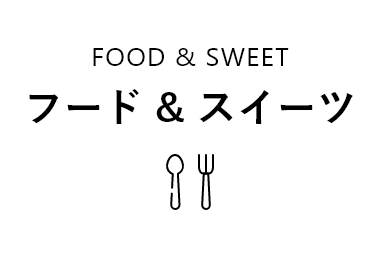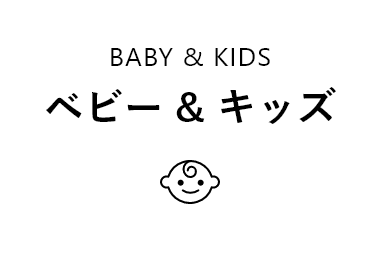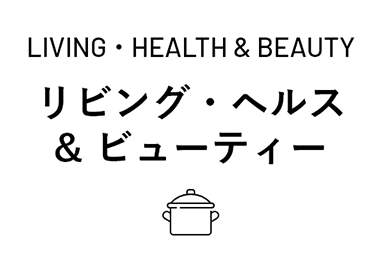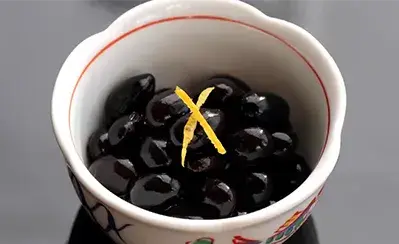カテゴリから選ぶ
初詣はいつまでに
行けば良い?
目安の時期を過ぎた場合の参拝についても解説!
初詣は、松の内期間にお参りするのが一般的ですが、立春頃になっても遅すぎることはありません。
いつでも万全の体制でお参りできるよう、神社と寺院へ参拝するための基本的なマナー、お賽銭や願い事の考え方についてまとめました。
初詣とは?
初詣は、お正月の恒例行事の一つです。
具体的には年が明けて初めて神社・寺院を参拝することを指します。
初詣の起源は、大晦日から元日の朝まで不眠不休で寺社にこもって行う年籠り(としごもり)と言われています。
年籠りでは、大晦日の夜に参ることを除夜詣(じょやもうで)、元旦に参ることを元日詣(がんじつもうで)と呼びました。
時代が移り変わるにつれて、元日詣を元にした新しいお参りの形として定まったのが、現在の初詣とされています。
ちなみに「初詣」という言葉が使われ出したのは大正時代で、意外と歴史は長くありません。

初詣が一般的になる以前は、恵方参りというお参りが行われていました。
恵方参りは、住んでいる地域の氏神様が祀られている寺社や新年の恵方に位置する寺社に参拝する習わしです。
一年間の感謝を伝え、新年の平安を願うという思いは変わりませんが、時代の変遷によって、お参りの形そのものは少しずつ変化しています。現代の初詣も、しばらくしたら少しずつ形が変わってくるかもしれませんね。
初詣はいつまでに行くと良い?
初詣は、できれば松の内の期間中に行くと良いとされています。
しかし松の内に参拝できない場合は、無理のない日取りを選んでお参りすれば問題ありません。
また、寺社が開門している間であれば、何時でもゆっくりお参りできます。
一般的には松の内期間中
松の内とは、門松やしめ飾りを飾っておく期間のことです。
門松やしめ飾りは、お正月の間、年神様をお迎えするのに重要な飾りであり、こうした「松」を飾っている期間を松の内と呼びます。
地域によっていつまでを松の内とするかは、若干違いがあります。
関東地方は、1月1〜7日まで、関西地方では1月1日〜15日までとしている地域が多いようです。
初詣といえば1月1日〜3日の三が日にお参りするという方も多いかもしれませんが、松の内ならいつでも参拝ができます。
松の内期間中の参拝が難しい場合は?
松の内までに参拝をしようという考え方のほかに、立春までの間に参拝すれば良いという考え方もあります。
立春は節分の翌日にあたります。2月1日は旧正月でもあり、節分が2月3日、2月4日が立春となります。
新型コロナウイルス感染症感染防止対策の一環で、2月まで参拝期間を延長し「分散型初詣」を呼びかける神社や寺院も増えてきました。2月15日の旧小正月までを参拝期間とする寺社もあります。
三が日の混雑を避けてお参りしたいという人は、この時期を検討するのもおすすめです。
参拝に適した時間帯はある?初詣に行ってはいけない日はある?
初詣には、特に定められた参拝時間はありません。
また、行ってはいけない日も特にありません。
しかし、寺社が開門している時間帯に参拝できるよう注意してください。
三が日や松の内の期間は、深夜や早朝も開門している神社、寺院が多いかもしれませんが、それ以降は閉門時間が早い可能性もあります。
できればお参りする前に、開門時間帯を調べておくと良いでしょう。
また、いくら混雑しているからといって、慌てて参拝するのはよくありません。
落ち着いてお参りできるように、時間に余裕をもって参拝しましょう。
一般的に三が日の午後の時間帯、1月4日以降は、どの神社、寺院も混雑が解消される傾向にあるので、比較的ゆっくりと参拝できるはずです。
初詣の参拝時に知っておきたいマナー
初詣の参拝は、神社と寺院で若干マナーが異なります。
どちらにも安心してお参りできるよう、基本のお作法をまとめました。
お参りのお作法(神社)
神社では、鳥居をくぐる時に15度ほど腰を曲げて軽く一礼します。くぐる時は中央を避けるようにしてください。
手水所(ちょうずしょ)で心身を清めてから、拝殿に向かいます。この時、左手、右手、口、柄杓の柄という順番に水で清めます。
神前では、まずお賽銭を納めて鈴を鳴らし、姿勢をまっすぐにして腰を90度に曲げ、二礼します。次に手を合わせて、二度拍手したら静かに目を閉じてお参りをします。
最後には深く一礼しましょう。

お参りのお作法(寺院)
一礼して山門をくぐります。
手水所では、左手、右手、口、柄杓の柄という順番に心身を清めます。
また、香炉がある場合は線香を供えましょう。線香は邪気やけがれを払うとされています。
賽銭箱の前では一礼してからお賽銭を納めます。
鐘をついたら手を合わせ、静かにお祈りをします。
最後には深く一礼しましょう。
本堂内で参拝する場合は、ご本尊の前でまず焼香をします。

木魚が置いてある場合は、たたきながらお経を唱えます。焼香の回数やお経の唱え方は宗派や寺院によって異なるので、参拝した寺院に従いましょう。
お賽銭の金額
お賽銭は、神様へ感謝の気持ちを込めて納めるものです。
無理のない範囲で、これと思う金額を納めましょう。
よく納められている金額は、縁起の良い語呂合わせになる5円(ご縁)、5円玉二枚の10円(重ね重ねのご縁)、25円(二重のご縁)、5円玉9枚の45円(終始ご縁)などです。
反対に、10円玉のみの10円や500円は、「遠縁」や「これ以上の硬貨(効果)がない」と読めるため敬遠されることがあります。
紙幣を納める場合は、住所と名前を記入した白い封筒に入れましょう。
願い事の数
初詣の願い事は、いくつしてもマナー違反ということはありません。
しかし、ご利益を授かれるようある程度内容を絞るのが良いとされています。
また、お賽銭を納めたらまず、1年間のお礼と報告をするのが良いとされています。
しっかり旧年の報告と感謝を伝えた上で、新たな願い事と祈りを捧げましょう。
さらに、初詣で願い事をする際は、名前と住所をしっかり伝えた上で、帰りも寄り道せずにまっすぐ帰宅するのが良いと言われています。
まとめ
寺社への参拝は旧年の感謝を伝え、新しい1年の平安を祈願する大切な風習です。
マナーを守って心からの祈りを捧げましょう。
混雑を避けてゆっくりお参りしたい方は、松の内を過ぎた1月下旬〜2月初めの参拝がおすすめです。
更新日:
2023年11月1日