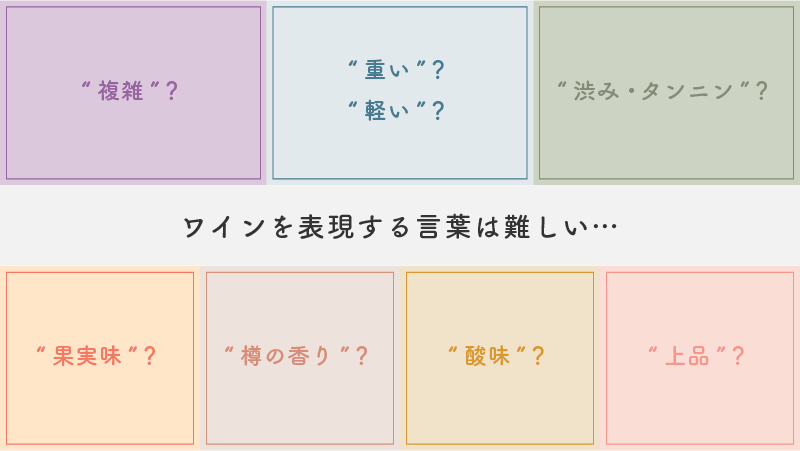
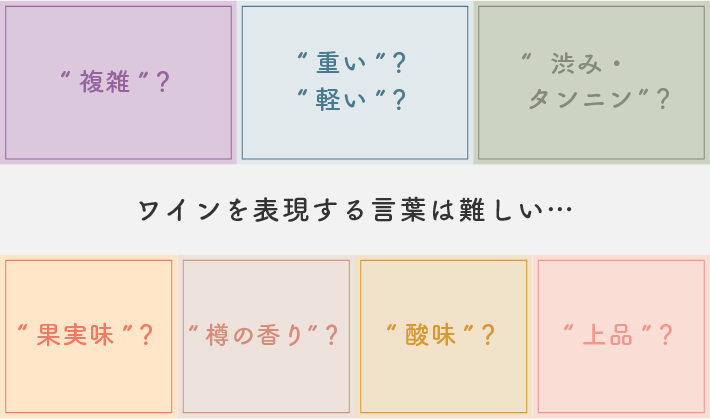
ワインがよくわからない理由、2つ目は「言葉」の問題です。
みなさん、ソムリエやワインマニア特有のトークを見聞きしたことはありませんか?
「干し草の香りが鼻に抜けるね」とか「このワインのテロワールは」とか。
ちょっと意味がわからないし、なんだか入っていきづらいですよね。
でも、こういった言葉が使えなくても全然気にする必要はありません。
だって、「干し草となめし皮の香りが鼻を抜け、ブルゴーニュの大地が見える・・・」なんて言うより、「おいしい!」「これ、軽くて料理に合うね」「うわ、渋いけどクセになる」と表現した方が楽しく飲めるはずです。
そう、ワインを楽しむために、専門用語は不要。「おいしい」とか「好き」で十分なんです。それで「素人っぽい」とか「バカっぽい」と思われることはありません。
ただし、自分に合ったワインを選ぶ際に知っておくと便利なワードはいくつかあります。それは、「干し草の香り」といった高尚な表現ではありません。味の指針になる、「甘い」「辛い」「渋い」「サッパリ」といった感じの、気取っていないワイン界の共通用語たちです。また、言葉がわかれば味の理解も深まります。飲みながら「あ、これが複雑な味なんだな」と納得できるようになると、俄然ワインが楽しくなってくるはずです。
これだけ知っておけば恥をかかない!ワイン界7つの「共通用語」とは?
① 複雑
ブドウ以外のいろいろな味(樽や動物、鉄などの本来ぶどうから出るはずのない味や香り)がするワインは、「複雑」と言われます。複雑さは、つくれてから時間が経ったり、樽で熟成させたり、何種類からのブドウを混ぜてつくることで生まれます。簡単に言えば、出来上がってから1週間後より1年後、2種類のブドウを使ったワインより6種類のブドウを使ったワインのほうが、より複雑な味わいになるということですね。
② 重い⇔軽い
主に赤ワインで使われる言葉です(白ワインは甘さや酸味の種類で表現します)。
重さは、文字どおり味ではなく触感を指します。口に入れたときに舌に乗っかる感じがしたら「重い」、さらりと流れたら「軽い」。それぞれ、別名「フルボディ」「ライトボディ」と呼びます。
あえて味の違いを表すと、いろいろな要素が混ざった「重い」ワインはコクが強く、逆に「軽い」ワインはフレッシュでフルーティと言えます。
③ 渋み(タンニン)
こちらも赤ワインで使われる言葉です。赤ワインの好みを分ける、重要な要素になります。
渋みは、タンニンの量によって決まります。口に入れたとき、歯茎がぎゅっと引き締まる感覚がしたら「タンニンが強いワイン」(実際、タンニンは唾液と結びつく性質があるので、物理的にぎゅっと締まる感じがするんです)。飲みにくさにもつながるので、初心者には苦手な人が多いですね。
ただ、渋みにはお肉の脂をリフレッシュしてくれる効果もあるため、脂身の多いお肉料理にはタンニンの強いワインが欠かせません!みなさんにも「赤ワイン=肉に合う」イメージがあると思いますが、これはタンニンのおかげ。逆に言えば、渋みが強くない赤ワインを無理やり肉料理に合わせる必要はないとも言えます。
④ 果実味=ジューシー・フルーティ
一緒くたにされがちなこの3つの言葉ですが、じつはそれぞれ次のような意味になります。
果実味=ジューシー=(ブドウ本来の味)
フルーティ=香り
「果実味が豊か」や「ジューシー」は飲んだ時に舌で感じる味、「フルーティ」はワイングラスから立ち上がる香りや鼻から抜ける香りだと理解しましょう。香りはフルーティだけど味はジューシーじゃない、フレーバーティーのようなワインもあるということです。
⑤ 樽の香り
樽香はチョコレートやコーヒー、少し焦げたトースト、プリンのカラメル部分などいろんな形で表現されますが、要は香ばしさが特徴です。
樽については誤解している人が多く、大きな声で言いたいことがあります。
「樽で熟成=高級=おいしい」じゃありません!
とある有名な高級ワインに樽の香りがついていることから「樽の香り=高級ワイン」というイメージが世界中に広がり、造り手がこぞってワインを樽で熟成させ始めた時期がありました。でも、樽の香りは無理やりつけたところでおいしいワインにはなりません。
⑥ 酸味
白ワインの酸味には、大きく分けて「ヨーグルトやヤクルトのようにまろやかなな酸(乳酸)」と「熟していないリンゴのようにシャープな酸(リンゴ酸)」の2種類があります。
基本的に白ワインにはリンゴ酸が含まれているのですが、とくに「シャルドネ」という品種で酸味が強すぎる場合など、味をまろやかにするためにリンゴ酸を乳酸に変える「マロラクティック発酵」をほどこします。
同じ品種のぶどうでも、ヨーグルトのような酸とリンゴのような酸で味わいはまったく違います。
⑦ 上品
「上品な味」ってわかるようでわからないような代表的な言葉かもしれません。なぜわかりづらいかというと、「上品」という言葉は、味そのものというより「出来映え」を表すものだから。品種を問わず、生産者の狙いどおりの上質なワインができたときに使われます。
全体的に渋みや酸味、甘味などのバランスがよく、まとまりがあるワインが「上品」。
ですから上品=こんな味、と特定の具体的な味があるわけではないのです。「上品」という言葉を聞いたら、「うまくつくられた上質なワイン」という褒め言葉だと考えてください。
ここまでに挙げた7つの言葉が、まず覚えておくべきワイン界の「共通用語」です。