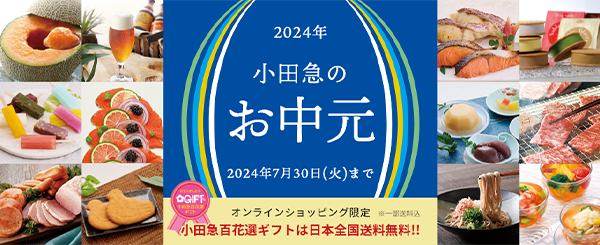カテゴリから選ぶ

お中元は、贈る場合にも受け取る場合にも、覚えておきたいマナーがいくつもあります。お中元は日頃の感謝をかたちにした夏のギフトなので、お互いに気持ちよくやり取りできるよう、必要なマナーをおさえておくことが大切です。
そもそもお中元の意味・目的は
お中元は日頃お世話になっているお礼を形にしたものです。贈ることで、感謝の気持ちと夏のごあいさつを伝えることができます。
お中元の目的
お中元を贈るのは、日頃お世話になっている方へ感謝とごあいさつを伝えるためです。地域によって違いはありますが、大体7月初旬から7月15日頃の期間に贈ります。暑さが厳しい時期に贈ることで、「暑い日が続きますがお元気ですか?」と相手を気遣う気持ちを込めることができます。贈る時期は、ちょうど年明けから半年ほど経ったタイミングなので、「半年間お世話になりました」、「続く半年もよろしくお願いします」という節目のごあいさつにもなります。
お歳暮との違い
お歳暮も、感謝の気持ちと相手の健康を願う気持ちを込める点は、お中元と変わりません。しかし、贈る時期に違いがあります。お歳暮は、日頃の感謝と「来年もよろしくお願いします」という気持ちを込めたギフトになるので、年の瀬に近い12月1日〜12月20日頃に贈るのが一般的です。
お中元は年明けから半年のタイミングで贈るのに対して、お歳暮は一年が終わる12月に贈ります。お中元は半年間の感謝の気持ちを伝える、お歳暮は一年間の感謝の気持ちを伝えるというのが、お中元とお歳暮の違いです。
暑中見舞いの違い
暑中見舞いは、挨拶状(ハガキ)と思われている方も多いかもしれません。しかし、夏の贈答品も暑中見舞いで贈ることができます。お中元は地域によって若干期間に差があるものの、暑中見舞いは全国的に7月15日〜8月7日頃(立秋)を目安に贈ることになっています。
暑中見舞いも、夏の暑さの中で相手の健康を気遣う気持ちが込められる贈り物です。そのため、お中元の時期を逃してしまったら、暑中見舞いとして贈れば問題ありません。
お中元を贈る際のマナー
お中元の相場
お中元の相場は、親しい間柄や家族・親戚に贈る場合、3,000円〜5,000円で選ぶのがふさわしいとされています。特にお世話になっている方や、ビジネス関係の目上の方へは、3,000円〜10,000円の範囲で相手との関係性に応じて選ぶのがおすすめです。お中元は、一度限りではなく毎年贈るのが基本のマナーとされています。最初だけ高額なものを贈って、次から金額を下げることはマナー違反とされているので、毎年贈っても負担の少ないギフト選びをすると安心です。
お中元の熨斗の選び方・書き方
お中元ののし紙は、贈るものによって選ぶものが変わります。魚介類や肉といった生もの、ソーセージなどの加工食品を贈る際は、熨斗のないのし紙を使います。それ以外のギフトは、熨斗のついたのし紙を使います。これは熨斗が「伸しアワビ」を起源とする縁起物であることから、生ものとアワビが重ならないようにする配慮とされています。
表書きは、ボールペンではなく毛筆や筆ペンを使って書きます。近年はマジックペンを使っても失礼にはなりません。
送る時期
お中元を贈る時期は、地域によって異なります。一般的には、7月初旬〜7月15日頃がお中元の期間とされていますが、この時期にお中元のやり取りをする地域は関東と東北のみです。北海道は7月15日〜8月15日の間、東海・関西・中国・四国は7月中旬から8月15日がお中元の期間とされています。九州は最も遅く、8月1日〜8月15日がお中元の期間です。都市部とそれ以外の地域で贈るタイミングが異なる北陸、旧暦に従うため毎年期間が異なる沖縄など、全国で大きな違いがあります。贈る前には、相手の地域の風習を調べてから贈るようにすると安心です。
お中元を受け取る際のマナー
お中元を受け取ったら、お礼の連絡をしたりお礼状を送ったり、感謝の気持ちを相手へ伝えます。お返しは必ずしも必要ではありません。
お礼の連絡をする
受け取ったら、すぐにお礼の連絡をしましょう。本来は、お礼状を書くのが正式なマナーではありますが、現代ではメールや電話でお礼を伝えても良いという風潮になりつつあります。時間が経つと失礼になるので、なるべく早くお礼を伝えるのがポイントです。親しい間柄の知人や家族・親戚であれば電話でお礼を伝えるのも良いでしょう。上司や取引先など、ビジネス関係の方からお中元を受け取ったら、3日〜1週間以内にハガキや手紙で挨拶状を出すのがマナーです。
お礼状の書き方
お礼状を贈る時期は、暑中見舞いのタイミングと一致しているため、「暑中お見舞い申し上げます」という書き出しにすると、スムーズに書きやすくなります。お礼状が遅くなった場合は、「残暑お見舞い申し上げます」と書きましょう。ビジネスシーンや目上の方などフォーマルな相手には、縦書きで書くのが基本です。カジュアルな間柄へのお礼状なら、横書きでも失礼にはなりません。
お礼状には、お中元を受け取ったことと感謝の言葉、相手の近況や体調を気遣う言葉を入れて、結びの言葉とし、日付と差出人名を書きます。
お返しの品について
お中元のお返しは、基本的になくても構いません。日頃の感謝を込めて贈るギフトであることと、一般的に、部下から上司へ、弟子からお師匠さんへ、など目下の人が目上の方へ贈るギフトであることがその理由です。しかし、お返しをしない分、お礼を伝えるのはとても大切なマナーになります。お礼状、電話やメールでのお礼いずれかをしっかりと行い、相手の気遣いに対して感謝の気持ちを伝えましょう。お返しをしたい時にお中元の時期が過ぎていたら、「暑中見舞い」あるいは「残暑見舞い」として贈れば問題ありません。
まとめ
お中元は贈る時期やのし紙の選び方など、贈る側が気をつけるべきマナーがいくつもあります。特に、地域によって贈る時期は差があるので、贈り物選びは早めにしておくと安心でしょう。そしてそれと同じように、受け取る場合にもお礼の連絡をするというマナーがあります。熨斗と水引が印刷されたのし紙や、メールでのお礼など、時代の変化によって考え方やとらえ方が変わってきたこともたくさんあるので、知識をアップデートさせながらお中元という伝統と向き合っていきたいですね。
更新日: 2024年2月1日